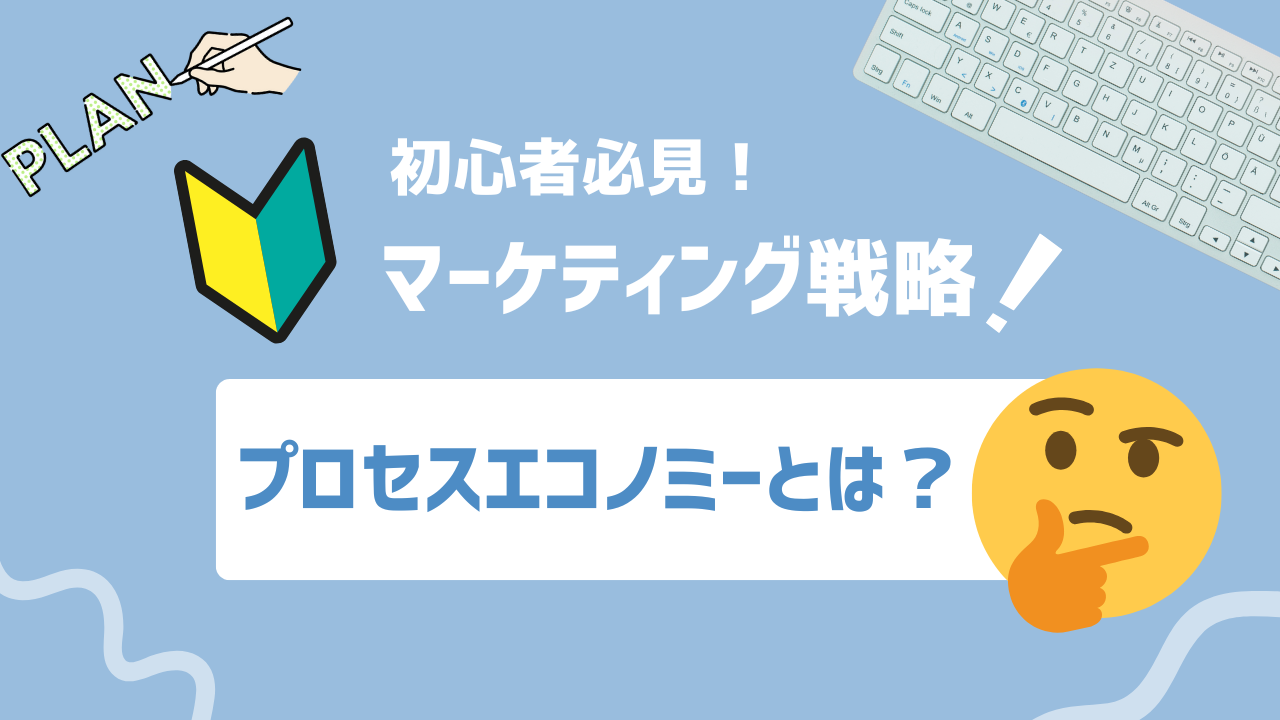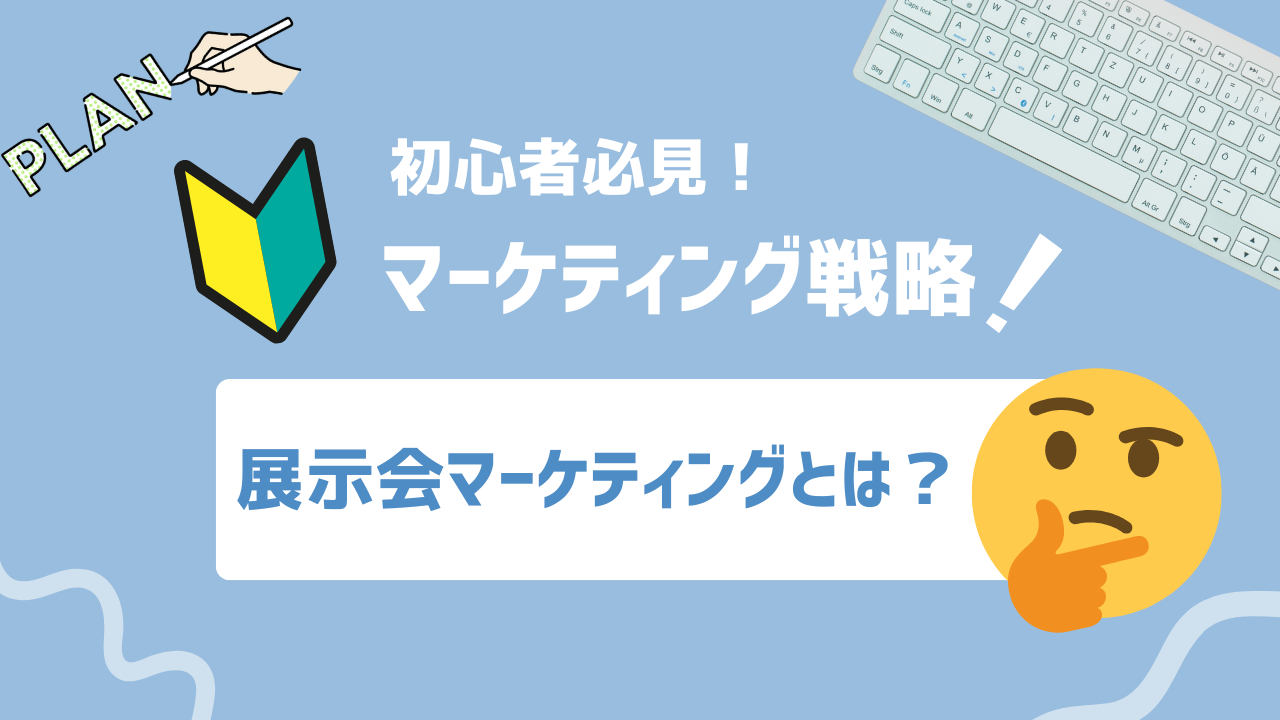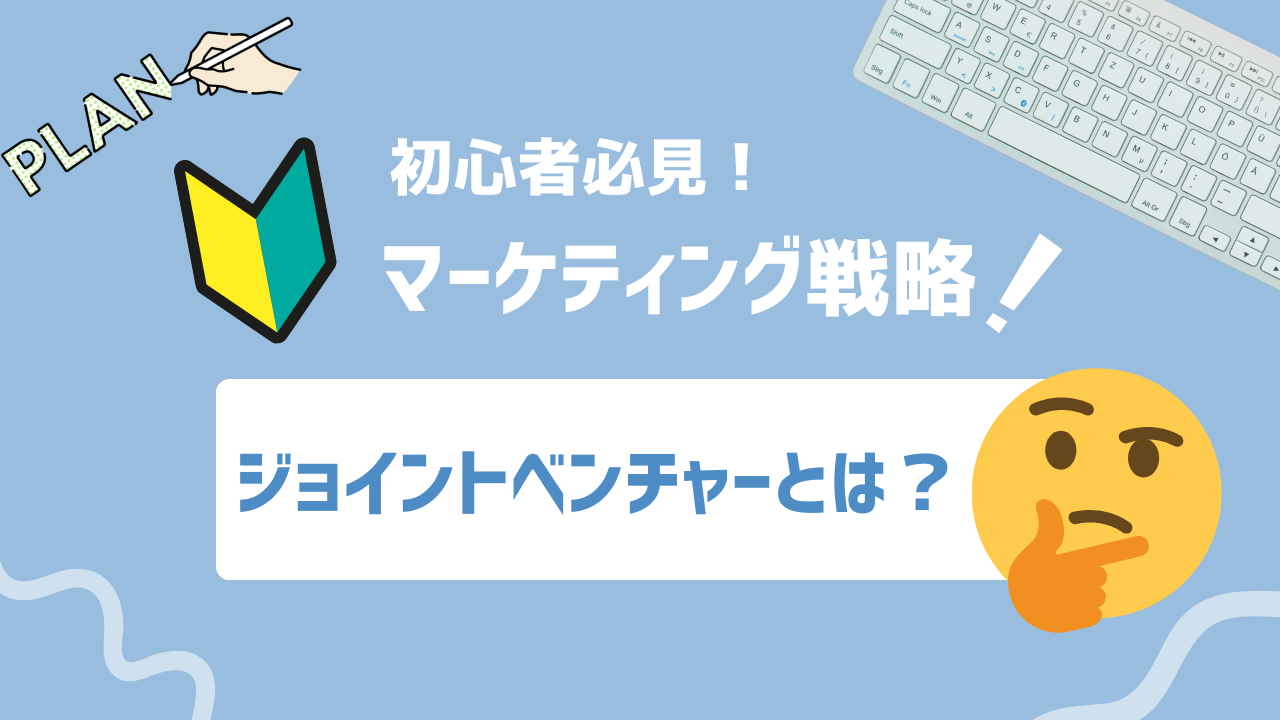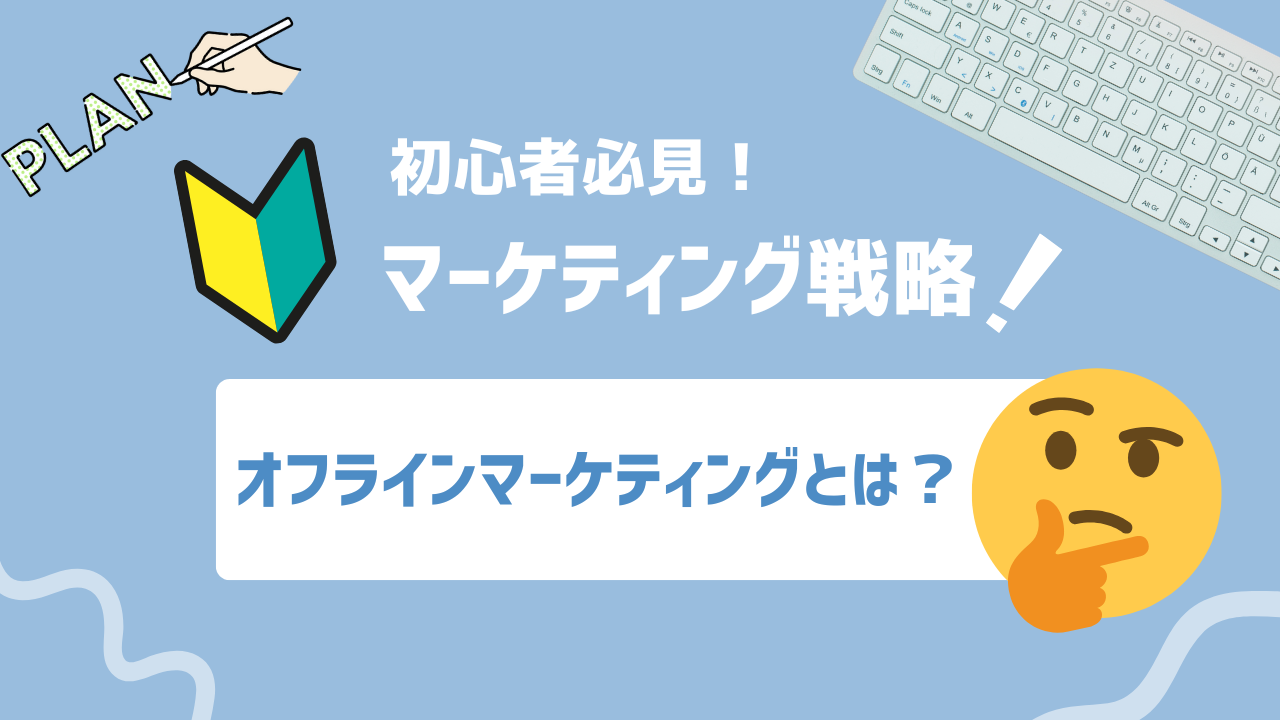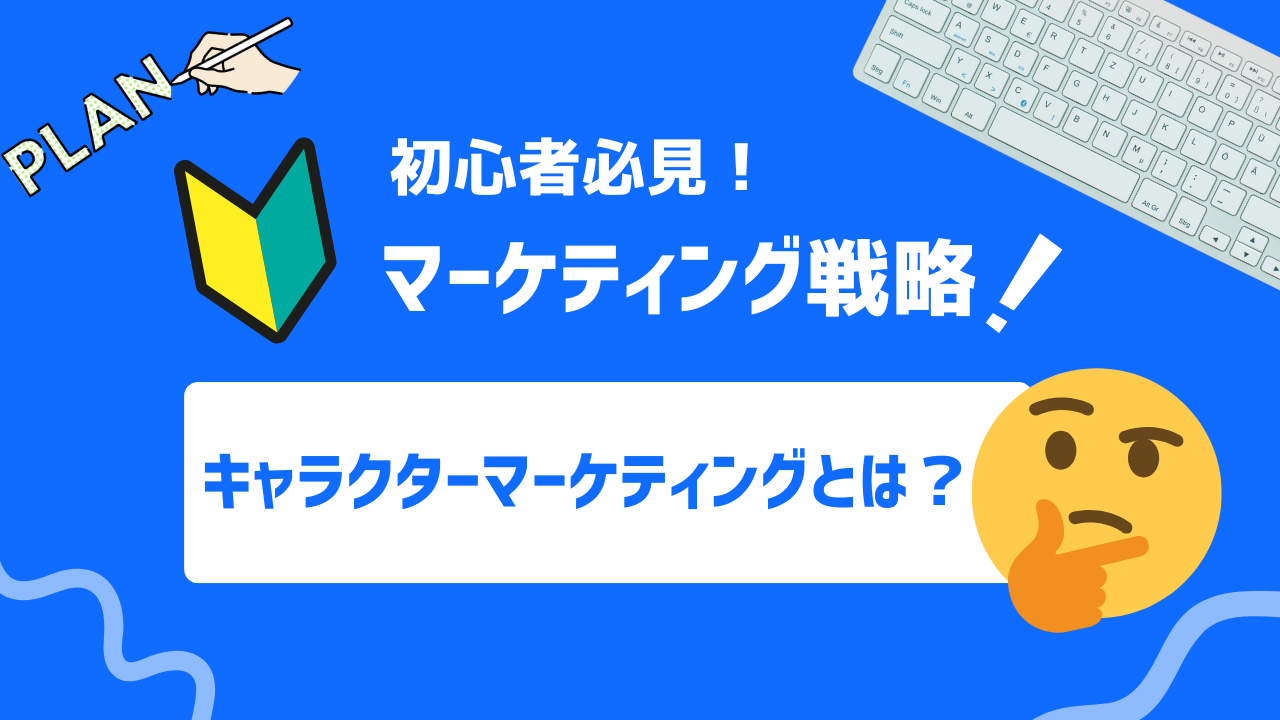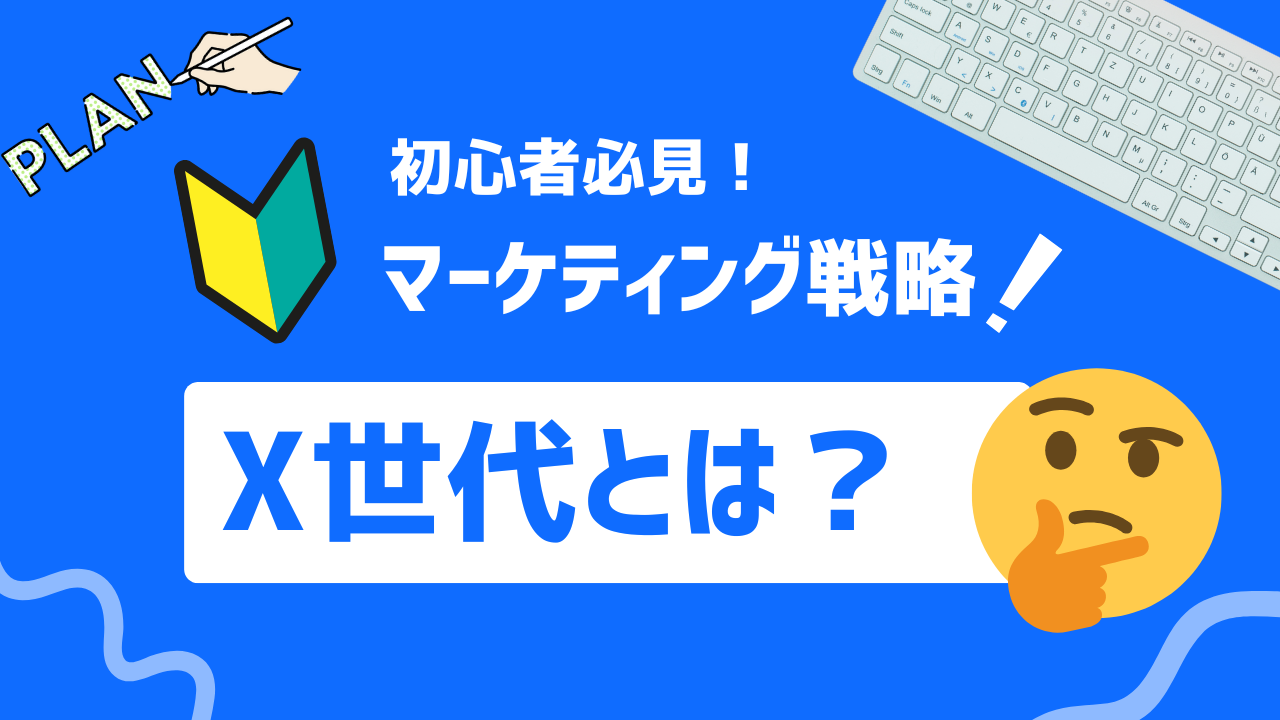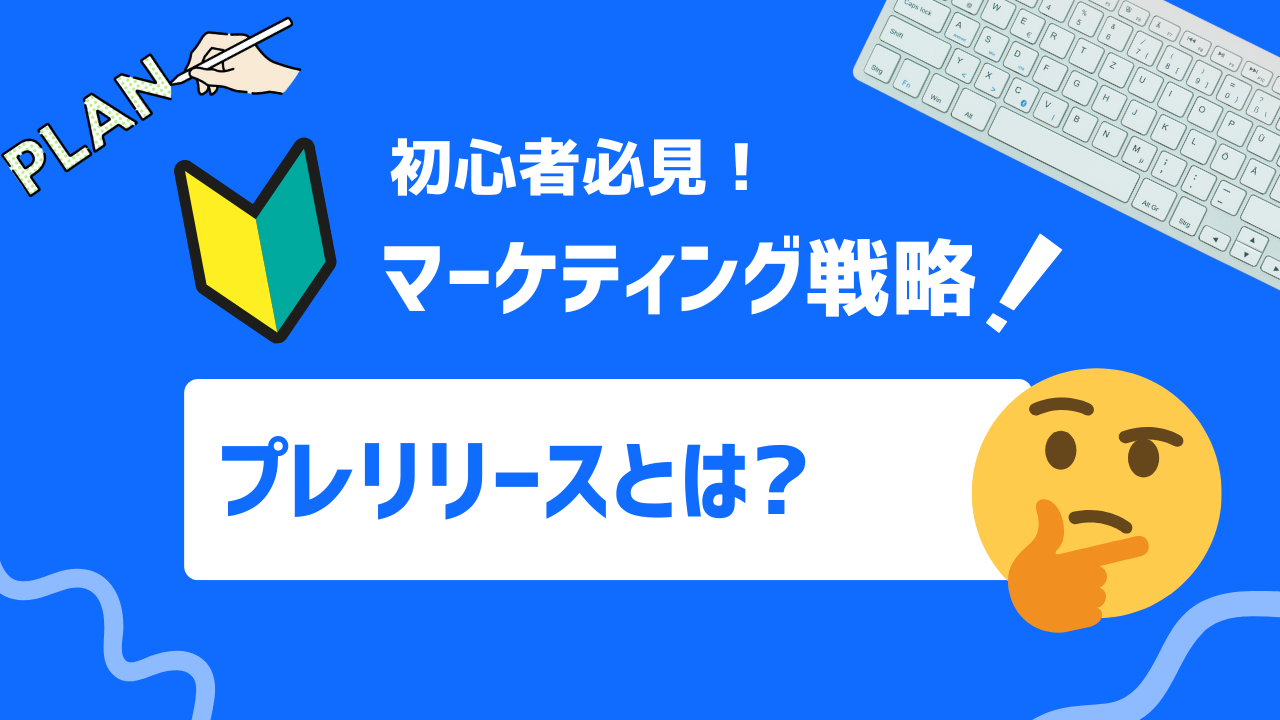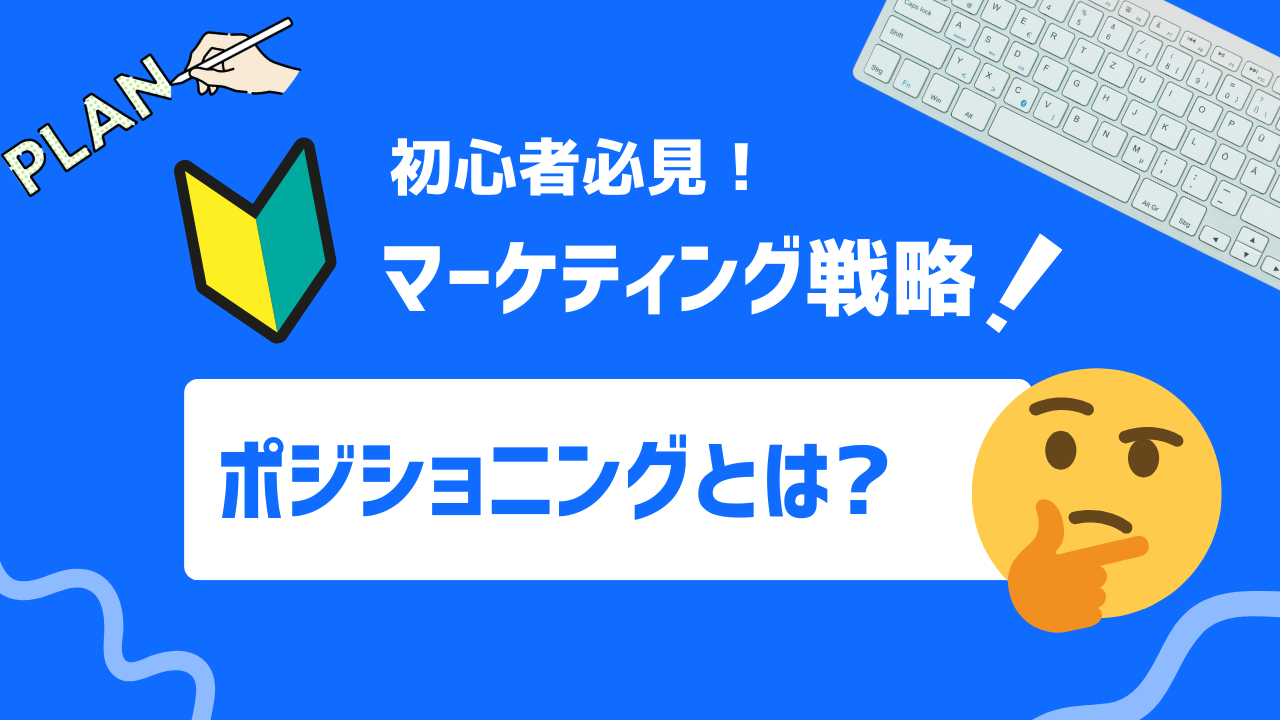【2025年最新】クロスメディアとは?メリット・デメリットや事例、成功のポイントを徹底解説!

クロスメディアとは、テレビやSNS、雑誌、イベントなど複数のメディアを連携させる戦略のことです。より多くの消費者にリーチし、相乗効果を生み出せます。本記事では、クロスメディアの特徴やメリット・デメリット、成功事例について解説します。
目次
クロスメディアとは?
クロスメディアとは、複数の異なるメディアを連携させて情報を発信する手法のことです。テレビ、雑誌、SNS、ウェブサイト、イベントなどの異なるメディアを組み合わせ、相互に影響を与えながらコンテンツを展開することを指します。例えば、「詳しくはWebで」という締めくくりのCMや広告は、テレビや雑誌などのメディアで広範な層にアプローチし、そこからホームページに誘導するというクロスメディア戦略の一例です。
メディアミックスとの違い
クロスメディアとメディアミックスは似ている部分もありますが、目的やアプローチ方法に違いがあります。
| 項目 | クロスメディア | メディアミックス |
| 目的 | 異なるメディアを連携させ、一貫したメッセージやコンテンツを展開し、相乗効果を生み出す | 異なるメディアを使い分け、ターゲットに最適なメディアで効率的に情報を届ける |
| 特徴 | 異なるメディアが連携して統一感のある体験を生み出す | 各メディアが独立して役割を果たし、ターゲット層にリーチすることを重視 |
| メディアの連携 | メディア間で明確な連携と誘導がある(例:「詳しくはWebで」) | メディア間での連携は必須ではない(例:異なるメディアで別々のキャンペーンを行う) |
メディアごとの特徴
クロスメディアは、異なるメディアを連携させる手法です。テレビや新聞、SNSなど、それぞれのメディアの役割と特徴についてご紹介します。
| メディア | 役割 | 特徴 |
| テレビ | 大衆向けに認知を拡大する注目を集める | 広範囲にリーチできる視聴者の関心を引きやすい |
| 雑誌・新聞 | 信頼性の獲得詳細情報の提供リアルタイムで広告を展開 | 深堀りした内容や専門的な情報を提供できる信頼性が高い |
| SNS | リアルタイムで情報を拡散ユーザーとのエンゲージメントを促進する | ユーザーとの双方向コミュニケーションが可能即時性が高い |
| ウェブサイト | 詳細な情報提供商品購入・申し込み誘導 | 24時間アクセス可能具体的な情報を提供できる |
| イベント | 直接的な接触を提供顧客との関係を深める | 体験型であるため特別感があるリアルな反応を得られる |
クロスメディアのメリット3つ
単一のメディアに依存せず、複数のメディアを活用することでブランドやキャンペーンの効果を最大化することができます。ここでは、クロスメディアのメリットについてご紹介します。
広範囲にリーチできる
複数のメディアを連携させることで、ターゲット層に広くアプローチすることが可能です。テレビ、SNS、Webサイト、イベントなど、それぞれのメディアが持つ強みを活かすことで、より多くの消費者にリーチし、ブランドの認知度を大きく向上することができます。
不足情報を補える
それぞれのメディアが得意とする方法で情報を提供することにより、単一のメディアでは伝えきれない商品やサービスの詳細や補足情報を補完し合うことができます。これによって、ユーザーに対してより価値のある情報を届けることができます。
メディア別に効果を把握できる
各メディアの効果を計測し、比較や分析に活用することができます。どのメディアが最も効果的だったのかを把握することで、今後のマーケティング活動において、より最適なメディア配分を行うことが可能になります。
クロスメディアのデメリット2つ
クロスメディアには多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、クロスメディアのデメリットについてご紹介します。
コストがかかる
テレビ広告、SNS広告、イベントなど、複数のメディアを活用することで、総合的なコストが増加することがあります。そのため、予算配分について慎重に計画することが求められます。
運用の複雑さ
クロスメディアでは、遷移先のメディアに付加価値を持たせることが求められます。そのため、メディアごとに異なったコンテンツを設置する必要があり、各メディアの特性を十分に理解しておくことが必要です。
クロスメディアの成功事例
クロスメディアを活用することで、新規ユーザーの獲得や幅広いターゲット層へのリーチに成功した例をご紹介します。
妖怪ウォッチ
社会現象を巻き起こしたTVアニメ『妖怪ウォッチ』は、「妖怪メダル」を単なる玩具として販売するのではなく、雑誌の付録やアパレル商品などにも付属させることで、幅広い層にリーチしました。さらに、ゲーム、アーケード筐体、玩具などで妖怪メダルを活用できるようにし、各メディアが互いに連動することで大きな相乗効果を生み出しました。
あんスタ×プロセカ
人気ゲーム『あんさんぶるスターズ‼️』と『プロジェクトセカイ』は、コラボキャンペーンにおいてクロスメディア戦略を活用しています。片方のゲームをプレイすると、もう一方のゲームで使用できるシリアルコードが発行され、育成や進行に役立つアイテムを獲得できます。さらに、特設サイトでのコラボの詳細な解説や双方の声優が出演する記念生配信などを実施し、両タイトルのファンがゲームを横断して楽しめる施策を展開しました。このクロスメディア戦略により、大きな話題を呼ぶとともに、双方の新規ユーザー獲得にもつながりました。
クロスメディアを成功させるポイント3つ
クロスメディアを成功させるために押さえておくべきポイントをご紹介します。
コンテンツに統一感を持たせる
メディアごとに発信内容が統一されていないと、ブランドやキャンペーンの認知が分散してしまいます。どのメディアを活用する場合でも、核となるメッセージやアピールポイントを一貫して伝えることが重要です。例えば、テレビCMで訴求したブランドの価値を、SNSやWebサイトでも同じクオリティやビジュアルで発信することで、ユーザーに強い印象を与え、ブランドの認知度向上につながります。
メディアごとの特性を活かす
各メディアにはそれぞれ得意とする役割があり、その特性を理解して活用することが重要です。例えば、テレビCMでは映像と音声を活かしたインパクトのある表現で認知を高め、SNSではユーザーとの対話を促す投稿を行い、Webサイトでは詳細な情報を提供するなど、各メディアが持つ強みを最大限に活かすことで、より効果的なプロモーションが可能になります。また、各メディアが相互に補完し合うことで、ユーザーの興味を持続させ、他のメディアへ遷移する流れを作ることもできます。
ターゲット層を細かく分析する
メディアごとに主要な利用者層や消費行動が異なるため、ターゲットを細かく分析し、それぞれに適したコンテンツや発信方法を設計することが成功につながります。例えば、若年層向けにはSNSのショート動画を活用し、シニア層向けには新聞広告やチラシを活用するなど、メディアごとの特性を踏まえた戦略が重要です。
クロスメディアの注意点2つ
クロスメディアの効果を最大限に発揮するためには、炎上リスクへの対策や、適切なメディアの選定は欠かせません。ここでは、クロスメディアにおいて押さえておくべき注意点をご紹介します。
炎上のリスク対策をする
複数のメディアを活用することで認知や拡散力が高まる一方、不適切な表現や誤解を招く内容が含まれていると、予期せぬ炎上につながる可能性があります。特にSNSは拡散が速いため、一度問題が発生するとブランドのイメージが大きく損なわれることもあります。リスクを回避するためには、発信する内容を慎重にチェックし、各メディアに適した言葉選びや表現を心がけることが重要です。
適切なメディアを選択する
クロスメディア戦略では、ただ多くのメディアを組み合わせれば効果が得られるわけではありません。ターゲット層や目的に合ったメディアを適切に選択することが重要です。例えば、若年層をターゲットとする場合は、SNSや動画プラットフォームが効果的ですが、ビジネス層には業界専門誌やニュースサイトの活用が有効です。また、メディア同士の相性を考慮し、一貫性のある情報提供ができるよう設計することで、より効果的なプロモーションになります。
まとめ
クロスメディアは、異なるメディアを連携させることで、ブランドやキャンペーンの効果を最大化する手法です。メディアごとの特性を理解し、ポイントを押さえて活用することで広範囲にリーチでき、不足している情報を補完し合うことができます。しかし、コストや運用の複雑さなどのデメリットも存在するため、慎重な計画と戦略が求められます。商品やブランドの認知拡大を目指している方は、ぜひクロスメディアという戦略を取り入れてみてください。
この記事を読んだ方におすすめの記事はこちら

 ポスト
ポスト シェア
シェア